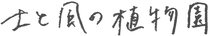12月25日は、クリスマス。
イエス・キリストの生誕を祝う日(降誕祭)で、今ではキリスト教徒以外の人たちも楽しむ世界的なイベントになっています。
クリスマスに欠かせないアイテムといえば、クリスマスツリー。
大きなもみの木に、さまざまなモチーフのオーナメントが飾られた光景は、見ているだけで幸せな気持ちになりますよね。
この記事では、ツリーを飾る習慣が根付いた経緯やもみの木を使う理由、ツリーに込められた意味について探ります。
意味を知ると、クリスマスの飾り付けがより楽しくなるかもしれません。
お家で手軽に飾れる、ミニサイズのクリスマスツリーも紹介しますよ。
小さくても、植物のフレッシュな香りが楽しめるアイテムもあるので、ぜひ最後までご覧ください。
クリスマスツリーを飾るのはなぜ?
1.クリスマスツリーのはじまり

クリスマスツリーの起源については諸説ありますが、キリスト教普及の動きの中で、古代ゲルマン民族の伝統的な祭りと、クリスマスとが融合したことがきっかけとされています。
ドイツでは、15世紀にクリスマスツリーを飾り付けた記録が残っていて、この頃からクリスマスツリーを現代のように飾る習慣が広まったのではないかと考えられています。
その後、イギリスやアメリカ、世界へと広がっていきました。

日本に初めてクリスマスツリーが入ってきたのは、1860年にプロイセンの公使が公館に飾ったという説が有力です。
1860年というと、日本は江戸時代末期で「文明開化」が始まる少し前のころ。
元号が明治になり文明開化が始まると、さまざまな西洋文化が日本に入ってきて、人々の暮らしや考え方が大きく変わっていきました。
クリスマスツリーを飾る習慣もそのひとつとして、日本で少しずつ馴染みのあるものになっていったのかもしれませんね。
2.もみの木を使う理由は?

クリスマスツリーにもみの木を使うようになったきっかけは、クリスマスツリーの起源とされる古代ゲルマン民族の伝統的な祭り「ユール」に遡ります。
ヨーロッパ北部に住むゲルマン民族は、寒さに強い樫の木を「永遠の象徴」として崇め、信仰の対象として崇拝していました。
日本でいう冬至(12月下旬)の頃に樫の木を飾ったり、丸太(ユール・ログ)を焚いたりして、お祭り(ユール)を行っていました。
中世に入ったのちに、キリスト教の宣教師がゲルマン民族をキリスト教に改宗させるため、「ユール」で使われていた樫の木の代わりに、もみの木を飾る習慣を広めたのが、クリスマスツリーにもみの木を使うようになったきっかけといわれています。

もみの木は、横から見ると三角形の形をしていますよね。
もみの木の三角形は、キリスト教の教えのひとつである、神(父)、イエス・キリスト(子)、聖霊が繋がる「三位一体」を象徴しているそうです。
ゲルマン民族を改宗させるために樫の木を切り倒したところ、切られた樫の木からもみの木が生えてきたという逸話も残っています。
常緑針葉樹のもみは、凍てつくような冬の空気の中でも、美しいグリーンの葉を茂らせていますよね。
キリスト教徒が、もみを三位一体の象徴としたのも、その力強さや神秘的な姿に古くから特別な想いを抱いていたからかもしれません。
3.飾る時期としまう時期
日本では、12月上旬にツリーなどを飾り始めるのが一般的。
12月25日が終わるとクリスマスツリーを片付けて、お正月飾りを出す家庭が多いですよね。

一方欧米では、11月末から12月上旬に飾り付けをし、年明けの1月6日ごろに片付ける家庭が多いようです。
キリスト教では、クリスマスイブまでのおよそ4週間は、キリストの降誕を待ち望む「アドベント(待降節)」という期間にあたります。
そして、クリスマスの12月25日から主の洗礼の祝日(※年によって異なる)までのおよそ2週間は、キリストの誕生を祝う「降誕節」という期間にあたります。
このアドベントと降誕節の期間にクリスマスツリーを飾る家庭が多いようです。
25日をすぎると一気にお正月ムードに切り替わる日本とは違っていて、興味深いですね。
ツリーに飾るオーナメントにも意味がある
クリスマスツリーに飾るオーナメントは、さまざまな種類がありますよね。
それぞれに込められた願いを知ると、オーナメントを選ぶ楽しさも増しますよ。
1.それぞれのモチーフに込められた意味
星

クリスマスツリーといえば、星を一番上に飾るのが定番。
キリスト教において、星はイエスの居場所を示す重要なものでした。
クリスマスツリーに飾る星は、イエス・キリストの降誕を知らせた「ベツレヘムの星」を表しているといわれています。
ベツレヘムの星がキリストの降誕を知らせたことで、3人の賢人がイエスの元へ導かれました。
天使
ガブリエルという天使を象徴しているとされています。
大天使ガブリエルは、聖母マリアがキリストを身籠ったことを伝えた天使。
「受胎告知」という名画にも登場します。

エル・グレコが複数描いた「受胎告知」のうちの1枚は、岡山県倉敷市の大原美術館で見ることができます。
エル・グレコの作品は日本に2点しかなく、とっても貴重なんです。
オーナメントボール

りんごや丸い形のオーナメントボールは、アダムとイブが口にしてしまった「禁断の果実」の象徴なんだとか。
りんごは寒い季節に保存が効くこともあり、昔から飾りとしても重宝されていたようです。
ベル

キリスト教では、ベルの音は喜びの象徴。イエス・キリストの誕生を知らせたのも、ベルであったとされています。
靴下

クリスマスイブの夜、大きな靴下をぶら下げておくと、サンタさんがプレゼントを入れてくれる。
子どもの頃のわくわくや喜びを体現したようなモチーフですよね。
クリスマスツリーに靴下を飾る習慣は、サンタクロースのモデルともいわれる聖ニコラウスの逸話から生まれたそう。
聖ニコラウスが、貧しい家族を助けようと真夜中に煙突から金貨を投げ入れたところ、全て暖炉で干していた靴下に入り、家族は金貨のおかげで幸せに暮らせたそうです。
ツリーに飾られた靴下の中には、家族で過ごす時間とか、家族の笑顔とか、何気ない幸せがたくさん詰まっているのかもしれませんね。
杖

杖の形のオーナメントは、「Candy Cane(キャンディーケイン)といいます。
赤や白のストライプ柄がポップで可愛いですよね。
この形は、羊飼いが使う杖をモチーフにしたという説があります。
迷っている人や困っている人を導く、助け合いの心を象徴しているともいわれています。
また、この杖を逆さにすると「J」の形になりますよね。
Jはイエス・キリスト(Jesus Christ)の頭文字であることから、この形になったという説もあります。
2.植物の息遣いを感じられるオーナメントもおすすめ
オーナメントというと、プラスチックやフェルト素材のものが多いイメージ。
きらきらと華やかなオーナメントはもちろん素敵ですが、本物の植物を使ったオーナメントは、人工的な素材とは違う特別感があります。
ひとつひとつ形が違っていて、素朴な温もりがあって。
飾る時にはその手触りも楽しめますよ。
パインコーンのオーナメント

パインコーンにヒバやユーカリの実などをあしらった、オーナメント。
パインコーンには「豊作への願い」や、「繁栄」といった意味が込められています。
松は昔から「不滅性」「不老長寿」など、縁起の良い木として知られているんです。
コットンフラワーのオーナメント

クリスマスカラーの白いコットンフラワーを使ったオーナメントです。
クリスマスカラーといえば、赤・緑・白の3色。
赤は「キリストが流した血」、緑は「永遠」、白は「純潔」を表します。
雪のような白さとふわふわの質感は、幸福をぎゅっと詰めこんだかのよう。
自宅で手軽に飾れるミニサイズのツリー
映画などで、立派なクリスマスツリーの下にプレゼントがたくさん並んでいる光景、一度は見たことありますよね。
このシチュエーションに憧れる方もいらっしゃると思いますが、本物のもみの木は手入れが大変ですし、保管にも困る方もいると思います。
今回は、手軽に飾れるミニサイズのツリーを紹介します。
ミニサイズとはいっても、本物のもみやドライフラワーを使っているので、香りはとっても本格的。
飾り付けのハードルは低くても、クリスマスを素敵に演出してくれますよ。
1.ガラス製のミニツリー

手のひらサイズの、クリアガラスでできたミニツリー。
もみや野ばらの実など、クリスマスカラーの植物を閉じ込めたシンプルなデザインです。
玄関、キッチン、小さな棚。
小さめだから、ちょっとした場所に、置き物のような感覚で飾れます。

透明なガラスの中に鎮座する植物たちを眺めていると、ミニチュアの世界に迷い込んだかのような気分が味わえますよ。
2.聖夜のホワイトツリー

針葉樹のイメージが強いクリスマスツリーですが、パンパスグラスやホワイト系のお花を使って、ホワイトクリスマス風に。
片手でも持てるちょうど良い大きさ。
場所をとらず、ちょっとしたところに飾っていただけます。

クリームホワイトのパンパスグラスが、優しく光を取り込んで、とても幻想的。
コットンフラワーや松ぼっくりが、素朴な温もりも感じさせてくれます。
いつもとは少し違うクリスマスの雰囲気を楽しみたい方におすすめです。
3.香りも楽しめるツリー風インテリア

香り高く、美しいグリーンが人気のサツマ杉。
もみの木と同じ針葉樹です。
枝を花びんに飾って、オーナメントを葉に引っ掛けると、小さなクリスマスツリーに早変わり。
とても手軽にクリスマス気分を味わえます。
オーナメントは重量感のない、軽めのものをお選びくださいね。
部屋に広がる針葉樹の香りに癒されますよ。

ドライフラワーやドライボタニカルとの相性も抜群なので、組み合わせて飾っても素敵です。
クリスマス感が強すぎないので、シーズンが過ぎても長く楽しむことができます。
ツリー以外にも!気分高まるアレンジメント
1.グリーンや木の実がたっぷりのクリスマスリース

こちらは、コットンフラワーやスパイス、木の実たちをぎゅっと詰め込んだクリスマスリースです。
1つのリースの中に10種類以上ものドライフラワーをあしらっていて、小ぶりでも存在感は抜群。
森の息吹を感じたい方にぴったりです。

こちらは、もみやヒバなどをたっぷりと使ったクリスマスリースです。
シルバーがかったグリーンや、柔らかい質感のグリーン。
同じグリーンでも質感や色味の異なるものを組み合わせることで、豊かな表情を感じられるように。
ホワイトやブラウンの要素を全体に足すことでグリーンの深みが増し、コントラストの美しさも際立ちます。

ツリーと同様、クリスマスリースの丸い形や装飾にも、ちゃんと意味があるんです。
ツリーに込められた意味について知りたい方は、こちらの記事もご覧くださいね。
リースとは?クリスマスを彩るリースの歴史と作り方
2.クリスマスカラーのスワッグ

ワイルドフラワーやこの時期ならではの実ものを束ねた、力強さと優しさ溢れるクリスマスカラーのスワッグです。
クリスマス感が強すぎないデザインなので、クリスマスが終わってもインテリアとして壁などに飾っておけます。
ラッピングをすると花束の状態になるので、贈りものにもおすすめです。
3.エバーグリーンのドライポプリ

静まりかえった冬の森を切り取ったかのよう。
ガラスの中に閉じ込めたのは、もみやスギなどの「エバーグリーン」です。
年間を通じて葉を一斉に落とす時期がない常緑樹のことを「エバーグリーン」とも呼びます。
もみやスギのように、葉の先が尖った針葉樹の大半は常緑樹なので、クリスマスシーズンによく使われるんです。

小さく、細かくなった「エバーグリーン」は、きっと今までに見たことがない姿。
上の層はハサミでカットして、下の層は粉砕した最後の形。
木の断面やごつごつした枝の表面が垣間見え、自然のエネルギーを感じます。
1年の中でも何かと忙しいこの季節。
リビングで、寝室で、深呼吸したくなるようなすっきりとした香りに包まれてください。
おわりに
クリスマスツリーにもみの木が使われる理由や、それぞれのオーナメントに込められた意味。
異教徒同士の信仰が混ざり合い、今に繋がる習わしが生まれるって、面白いですよね。
大きなツリーもとても素敵ですが、お家で飾るなら、やっぱり小さいサイズが場所も取らず、お手入れも簡単。
今回紹介したようなドライフラワーやドライボタニカルを使ったアイテムなら、香りや質感などフェイクグリーンにはない良さも楽しめますよ。

土と風の植物園では、自分でクリスマス飾りを作りたい方向けに、さまざまな花材も揃えています。
記事でも紹介したように、もみやサツマ杉の枝をフラワーベースに飾るだけでも、お部屋がクリスマスらしい雰囲気になりますよ。
ぜひオンラインショップを覗いて、クリスマス気分を盛り上げてくださいね。
Happy holidays!